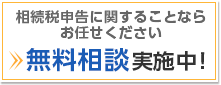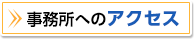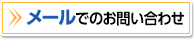公正証書遺言の作成
遺言書には、作成方法がいくつかありますが、内容に不備があったり法律に従った書式でなければ遺言書の効力を発揮できません。
また、遺言書の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成する場合には、検認が必要です。(2020年7月の法改正がされたあと法務局に保管した自筆証書遺言については検認の必要がなくなります。)
一方公正証書遺言は検認の必要がなく、公証役場で作成する為、公証人によってその場で遺言書に不備がないかチェックされるため、効力がない遺言書が作成される心配がありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場に保管される為、紛失の心配や、亡くなった後遺言書が発見されないなどの心配も不要です。
自筆証書遺言で作成し、ご自身で保管した場合には、亡くなった後遺言書が発見されないといった事があります。これではせっかく作成した遺言書も役割を果たさないものとなってしまいます。
公正証書遺言は、いつでも手軽に作成できる自筆証書遺言と比較すると、手間も費用もかかってしまいますが、確実に遺言書を残すことができ、遺言者の希望も確実に実現することができます。
公正証書遺言の作成方法
- ①2名以上の証人と公証役場へ出向く
公正証書遺言の作成は、遺言者が2名以上の証人と公証役場へ出向く必要があります。証人は遺言によって影響を受けることがない成人であれば誰でもなることができます。遺言者の相続の際に利害のある人以外であれば、ご友人などでも問題はありません。
証人になれない人は、推定相続人、未成年者、受遺者、その配偶者及び直系血族の人となります。
証人をお願いできる人がいない場合には、司法書士などの専門家に依頼するといった方法もあります。 - ②遺言者が遺言内容を公証人に口述する
聴覚や言語機能が不自由な方は、手話による申述や筆談でも可能です。 - ③公証人が遺言者の遺言内容を筆記する
- ④公証人によって筆記された遺言内容を遺言者と証人が確認する
遺言内容を公証人が読み上げ、閲覧させ、遺言者と証人が口述した内容と相違がないかを確認をします。 - ⑤遺言者と証人が署名・捺印する
- ⑥遺言が法のもとで作成されたものであることを公証人が筆記し、署名・捺印する
- ⑦遺言書の原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が交付される
上記の流れで公正証書遺言は作成されます。少々手間と費用はかかりますが、確実に遺言を残したい場合には、公正証書遺言が間違いありません。
遺言書作成について
【お問合せ受付時間】月〜金 9:00〜19:00
※18時以降はお電話に出られない場合がございます。予めご了承ください。
松山相続税申告相談センターでは、相続税に関するご相談を初回無料で受付けております。松山以外の方のご相談もお受けしておりますので、まずはフリーダイヤルよりお気軽にお問合せ下さい。
受注増に伴い業務の品質を維持するため、生前対策に関するご相談の受付を一時休止させていただいております。なお、発生した相続に関するご相談につきましては、引き続き承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。